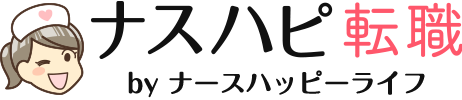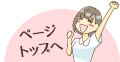訪問看護において療養者・家族との信頼関係を築く事は療養者が安心して在宅生活を維持していくためにとても大切になります。そのため訪問看護師は療養者を取り巻く環境においても他機関と連携して支援していく必要があります。
ここでは、そんな訪問看護において発生する人間関係の問題についてお話ししていきます。
主治医との間で発生する問題
在宅で療養者をみていく上で、主治医との連携は必須と言えます。そのため信頼関係はもちろん、治療に合わせたケアを行い、方針を統一させて関わっていく必要があります。
在宅に関わるのは、訪問看護指示書を出している下記のような医師が主治医となります。
- 病院外来の医師(訪問看護ステーションの直属)
- 自ら開業し、外来診療も行う往診医
- 在宅診療を専門に行っている医師 などになります
病院外来の医師や在宅診療を専門に行っている医師の場合、緊急時の対応も迅速になされ、医師との連携も取りやすいことが多いです。
外来診療を行っている往診医の場合、診療時間などに縛られやすく、他の医師と比較するとやや連携が取りにくいことがあります。
病院外来の医師や往診医との間で起こりやすい問題
病院外来の医師や往診医の診察は月に1回など回数が少ないため、医師は療養者の病状変化を把握しにくいのが現状です。そのため訪問看護師とのタイムリーな情報共有が難しいです。
解消策としては、月に1度の診察時に療養者の方に報告書を持参してもらい、報告・相談するという対応です。療養者や家族が直接医師に聞きにくい場合も看護師からの報告書があるとスムーズです。
また、総合病院などは医療連携室が設置されており、問題を抱えている療養者の診察結果や治療の詳細などは看護師同士での確認が可能です。スムーズな連携のためにも活用するとよいでしょう。
在宅診療の専門医との間で起こりやすい問題
最低でも月に2回以上は訪問診療を行っているため、療養者の病状の変化について共有しやすいです。訪問看護と同じ日に訪問診療を行う場合もあり、必要によっては出来るだけ重ならないよう日程を調整しなければなりません。
報告書はもちろん、電話での密な連携が大切になります。
このように、訪問看護師はどのような場合であっても主治医とは積極的に連絡・報告していく事がスムーズな連携につながります。
療養者・家族との間で発生する問題
在宅療養では病院での療養と比較すると、療養者の「その人らしさ」が出やすいのか個性の強い療養者の方が多いように感じます。まずはありのままを受け入れ、生活の中の療養者に合わせた関わりが必要といえます。
訪問看護師の担当を変更するときに起こりやすい問題
訪問看護は1人の療養者を複数名で担当する事もありますが、1人の看護師が毎週訪問する担当制を取っているところも多いです。
ずっと同じ看護師が関わることで、療養者にとっての安心につながりますが、担当看護師を変更するといった場合、療養者からの苦情につながったりします。
「あの看護師さんはもっとこうしてくれた」などケアのやり方などが定着しているため、担当を変更するときは十分な引継ぎが必要となります。
そうならないためにも、複数名で担当した方が緊急時など誰でも訪問できるなど看護師側のメリットがあります。
訪問看護の介入回数を減らす・終了するときに起こりやすい問題
在宅での療養生活ではなかなかゴールを見い出しにくいため、訪問看護をしていく中で療養者やその家族が自立に向かい訪問看護の必要性がなくなった時に、介入の回数を減らす・または終了させるのはとても難しいことです。
療養者やその家族が自立して生活できるようになることはとても良い事ですが、急に毎週来ていた医療者が訪問しなくなることは、やはり不安になるようです。
訪問する中で療養者・家族が自信を持って自立に向かう、そんな訪問看護師の関わりが重要と言えます。
療養者・家族間の考え方の違いにより起こりやすい問題
独居の療養者もいますが、支援する家族がいる療養者もいます。
医療依存度や介護度の高い方が生活を維持していく上で、そのような家族の存在はとても重要と言えます。しかし療養者と家族の間で考え方のずれが生じることがあります。
そんな時には訪問看護師が中立の立場で間に入って調整することも必要です。
このように、主体は療養者・家族ですから、その立場になって行動する事が大切です。
訪問看護ステーションとの間で発生する問題
訪問看護ステーション同士で関わる場面はそんなに多くはありません。
そのため、一緒に同じ療養者へ介入する場合は注意が必要です。
ステーションの都合などにより療養者の訪問が継続できない場合
ステーションの都合などにより療養者の訪問が継続できない場合は他のステーションに受け持ちを引き継ぐ事があります。
療養者が安心して在宅生活を継続できるように、ステーション間で十分に情報交換をしていきます。実際に療養者の自宅で同時訪問し、病状やケアに関して引き継いでいきます。
他にも訪問リハビリステーションが介入している場合
看護とリハビリで目標の刷り合わせをし、療養者が混乱しないよう統一した関わりをしていく必要があります。
このように、療養者・家族が安心して在宅看護を受けられるよう他ステーションとの連携・調整が必要です。
おわりに
人間対人間の関わりなので上手くいかない事も多いかもしれません。やはり訪問看護は経験がものをいう職場です。
そんな時は、経験の豊富な先輩看護師に対応してもらい、その姿勢をお手本にすると経験が浅くても自信が持てるようになります。