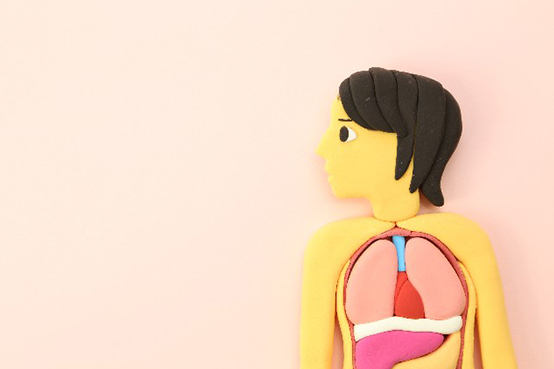
当サイトでは過去に「看護師だけでなくプラスで資格を習得して、スキルアップに繋げよう!」という記事で、看護師さんが取得するとキャリアアップに役立つ資格についてまとめています。
本記事では、上記記事で書かれていない「呼吸療法認定士」という資格について、仕事の内容から資格取得の流れ、試験対策までを3回に分けてシリーズでお伝えしたいと思います。
呼吸療法認定士とは?
正確には「3学会合同呼吸療法認定士」といいます。
- 日本胸部外科学会
- 日本呼吸器学会
- 日本麻酔科学会
この3学会が認定する制度で”呼吸療法のエキスパート”としての活躍が期待されます。内容は難しいのですが意外と人気が高く、毎年多くの受験希望者が集まります。
2014年現在、28495名の認定士登録がされています。
呼吸療法士の活躍
アメリカの呼吸療法士は大幅な医療行為が認められているのですが、日本ではあくまで所有資格の範囲内の業務しか認められていません。
つまり看護師がレスピレータ(人工呼吸器)の設定変更をしたり、医師の指示なくウィーニング(呼吸器離脱)等をすることはできません。
では、日本の呼吸療法士は何ができるのでしょう?
呼吸療法認定士の必要性は「それぞれの所有する国家資格により規定される業務範囲で
医師と共に医療チームを構成する」とされています。
そこで医師、看護師、臨床工学技師、理学療法士などによるRST(呼吸サポートチーム)を編成し、
- 人工呼吸中の患者のラウンド
- 主治医への提言
- ケア方法の指導
- ウィーニングへのアドバイス など
を行う活動が拡大しつつあります。
2010年診療報酬改定の際、呼吸ケアチーム加算が新設され、RSTの活動が診療報酬に貢献できることになりました。
呼吸療法士になるまで
認定試験ももちろん大変ですが、申請までの手順もなかなか大変です。
講習会への参加条件
- まず、申請時点で2年以上の実務経験を持つ看護師、理学療法士、臨床工学技士、
3年以上の資格を持つ准看護師であることが資格条件です。
そのため申請の際は、勤務先に実務経験の証明をもらわなくてはなりません。 - また、申請から5年以内に認定委員会が定める学会や講習会に参加し、ポイント(12.5P)以上を取得している必要があります。
これらの条件をクリアし、はじめて認定講習会への参加申し込みができます。
講習会参加から資格取得までの流れ
- 認定講習会の申し込みは春(4月頃)に郵送(特定郵便)で行いますが、人気が高いため
先着順で締め切られてしまいます。
そのため申し込みが開始される日の早朝に郵便局に並ぶことになります。 - 無事に受講資格が得られたら、夏(8月頃)に行われる2日間の認定講習会を受講します。もちろん遅刻、早退、欠席、居眠りをしたら受講証明はもらえません。
- そして冬(11月頃)になり、資格試験を受験します。
- めでたく合格通知が郵送されてきたら、期限内に所定の手続きを行い、呼吸療法認定士として登録されます。
まさに1年がかりで準備をする必要がありますので、認定を希望される方は早めに行動しましょう。
また、申し込み書類の期限などはかなりシビアなので、常に認定委員会のホームページを
チェックしておくことも大切です。
呼吸療法士になったあと
呼吸療法認定士の認定証明書がもらえますので、ぜひ職場の上司へ提出し、RSTへの参加を申し出ましょう。
呼吸療法士の待遇としてはまだまだ一般的ではありませんが、近年、呼吸療法加算が新設されたことで、今後は期待できるかもしれませんね。
資格更新は5年毎となりますが、次回更新時までに認定委員会が定める学会や講習会に参加し、所定のポイントを稼いでおかなければなりません。
認定後も継続して学習し、日々変化する呼吸療法の情勢に目を光らせておく必要がありますね!
★呼吸療法認定士についての関連記事はこちら











